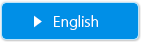活動状況
デジタル・エコシステム研究会
主 査 : 岡田朋之
幹 事 : 北村順生、脇浜紀子
研究会主旨:
今日の社会がグローバルな諸課題(地球環境、格差、安全保障等々)にとり囲まれるなか、持続可能な発展を実現しうる社会の制度設計や政策立案に向けて、ICTの果たす役割について考える。くわえて関西地域が有史以来日本の政治や文化、産業の極としても大きな役割を果たし、また本学会の設立以後は情報通信研究の中核のひとつを担ってきた経緯を踏まえて、当地域の発展にICTがどう資するかも交えた議論の展開をめざす。
2024年度 第1回 デジタル・エコシステム研究会開催のお知らせ
日 時:
2025年3月3日(月) 15:00~17:30 (18:00~ 懇親会 (会場付近))
場 所:KANDAI Me RISE - 関西大学 梅田キャンパス 4階ラボ (大阪市北区鶴野町1-5)
※オンラインでの聴講はございません。
テーマ:いま、万博に意味はあるのか?──国際博覧会とICTのこれまでとこれから
報告者:岡田朋之(関西大学)
討論者:永井純一(関西国際大学)
概 要:
今年4月13日より、日本では6回目、大阪でも3回目の国際博覧会として、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催される。開幕まであとわずかとなる中で、一般の人々の関心の低さや、開催そのものに対する批判の声も多くみられる。
万博の170余年の歴史の中で、情報通信技術(ICT)は展示の中の目玉としての役割を果たしてきた。その例は、1876年フィラデルフィア博(米国)でのグラハム・ベルの電話機、1939年ニューヨーク博(米国)でのテレビジョン、1970年大阪博でのワイヤレステレホン、2005年愛知博のスーパーハイビジョンテレビ(8Kテレビ)など枚挙に暇がない。しかしながら、デジタル・メディアとネットワークの発展した今日における万博の意義を疑問視する向きは、本学会員の中にも少なくないであろう。
今回の報告者は、2005年の愛知万博(愛・地球博)の折にこの領域における博覧会の意味を見いだし、以降のほぼすべての万博に足を運んで現地での視察と調査研究をおこなってきた。その知見をもとに、このイベントが21世紀のデジタルの時代に開催される意味を紹介する予定である。
また討論者としては、音楽フェスティバルについて、メディア論や文化社会学の立場からイベントの研究に携わってこられた永井純一氏を迎え、万博の開催にあたっての疑問点や、若い年代の関心を惹く上での課題を指摘してもらうことを通じ、今回の万博の抱える問題点や、可能性について議論を深めていきたい。
参加費:無料(事前申込制)
※本研究会開催後に開催される懇親会については懇親会費が必要となります。
懇親会費:4,000円(一般)、2000円(学生)
申込方法:件名を「デジタル・エコシステム研究会参加申込」とし、氏名、所属、連絡先(電子メールアドレスまたは電
話番号)を明記の上、下記メールアドレス宛までお申込ください。
※本研究会終了後に開催される懇親会に参加希望の場合は、2025年2月21日(金)までお申し込みください。
参加を申し込まれた方には、別途詳細をご連絡いたします。
申込先メールアドレス kenkyukai@jsicr.jp
- 2023年度 第2回研究会
「コンテンツプラットフォーム(コミックシーモア)について」 - 2023年度 第1回研究会
「グローバルトレンドから見る、これからの日本のデジタルオーディオ広告」 - 2022年度 第1回研究会
「倍速視聴の現在形 「作品の鑑賞」から「コンテンツの消費」へ」 - 2021年度 第1回研究会
「コンテンツツーリズムからメタ観光へ――ソーシャルメディア時代の観光を考える」 - 2020年度 第2回研究会
「「キャラ縁」の聖地~現実と仮想(虚構)を架橋する「キャラ」~」 - 2020年度 第1回研究会
「同時配信・見逃し配信 NHKプラスについての現状や課題」 - 2019年度 第2回研究会
「中国における自媒体の発展とジャーナリズム」 - 2018年度 第2回研究会
「radikoの進化とアーティストコモンズによる独自のメディアエコシステム形成の可能性」 - 2018年度 第1回研究会
「デジタル・エコシステムへの最適化を目論むニュースメディアの進化形
~アルジャジーラが仕掛けるデジタルオンリーメディア『AJ+(エージェープラス)』とは」